目次
ごぼうはガスが溜まる原因?
ごぼうには、水に溶けやすい「水溶性食物繊維のイヌリン、ペクチン」と水に溶けにくい「不溶性の食物繊維のリグニン、セルロース、ヘミセルロース」食物繊維が含まれています。水溶性食物繊維と一部の不溶性食物繊維は腸内細菌によって発酵されやすく「発酵性食物繊維」とも呼ばれています。これらが腸内の善玉菌のエサとなり、腸内で発酵されることで短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸など)を産生し、腸内環境を整えるなど健康効果をもたらします。そのため適量であれば食物繊維は便秘解消に役立ちます。食物繊維不足を原因とした便秘であれば、ごぼうの摂取が解消につながります。ただし、ごぼうを過剰に摂取すると下痢になる可能性があり、ガス(おなら)の原因になり得るでしょう。
ごぼうを摂取する際の注意点
ごぼうは適量であれば便秘解消に役立つものの、即効性はありません。便秘解消の効果を得るには、一定期間摂取し続けなければなりません。食物繊維は1日あたり、15~74歳の女性は18 g 以上、18~29歳の男性は20 g以上、30~64歳の男性は22 g 以上の摂取が推奨されています。
お腹にガスが溜まる原因
お腹にガスが溜まる原因には多くの場合、食事が影響しています。その他も含め、おもな6つの理由を解説します。
食事中の無意識な飲み込み
食事中に話をしたり早食いで無意識に空気を飲み込んだりしたことによって、お腹にガスが溜まるケースは多くみられます。体内に溜まるガスの70%近くが、無意識に飲み込んだ空気が原因とされています。ほとんどはげっぷとして排出されます。
暴飲暴食
食べ過ぎ・飲み過ぎや肉類を多く摂取することによって、内容物が腸内で異常発酵するとガスが発生しやすくなります。また、胃腸の機能が低下すると排出能力も下がり、ガスが溜まりやすくなります。炭酸飲料やビールなどもガスが溜まる要因です。
食物繊維・脂質が過剰に多い食事
肉類や高脂質な食事は悪玉菌を増やす原因となり、腸内のガスが発生しやすくなります。過度に摂取すると腸内にガスが溜まりやすく、お腹が張る原因です。脂質の多い食事は消化・吸収に長い時間がかかり、ガスの排出能力が低下します。
ストレス
ストレスもガスが溜まる要因になります。腸と脳の間には関わりがあり、消化管機能とストレスは結びついています。たとえば、緊張すると無意識に唾を飲み込みやすくなり、空気を飲み込みガスが溜まりやすくなるでしょう。
心身のストレスによって、消化管をコントロールする自律神経のバランスが崩れると、消化管の活動が低下したり異常に亢進(こうしん)したりして、ガスが発生しやすくなります。
慢性的な便秘
慢性的な便秘は、ガスが発生しやすくなります。大腸に便が溜まり発酵が進むことで、悪玉菌が増えるためです。大腸の機能低下があると、ガスの排出能力も低下し、ガスが溜まることにつながります。
お腹のガスを抜く方法:1.ツボを押す
ガスがつらいと感じる方のための補助的民間療法として、ツボを押す方法があります。ツボを押す場合は、1回につき6秒、痛気持ちいい程度の強さで押します。ただし、食事・入浴の前後1時間や飲酒時、満腹時、妊娠中や出産直後などの人は控えましょう。
腹結(ふっけつ)
腹結(ふっけつ)は、へその下約4.5cm(1.5寸)にある、便の停滞に対して効果があるとされるツボです。お腹に張りや圧迫感があり、便の停滞を感じる人はこのツボを押してみましょう。
大腸兪(だいちょうゆ)
大腸兪(だいちょうゆ)は場所を選ばず、座って押せるツボです。ウエストラインより下の腸骨あたり、身体の中央から左右それぞれ指2本分の位置にあります。大腸の働きが活性化され、ガスの排出を促すとされています。
天枢(てんすう)
天枢(てんすう)は、へその中央から真横に、左右それぞれ指2・3本分の位置にあるツボです。左右同時に、人差し指・中指・薬指をそろえて押しましょう。胃腸の働きが活発になり、ガスの排出がサポートされるといわれています。
お腹のガスを抜く方法:2.ストレッチをする
ツボを押すことに加え、ストレッチもガスを抜く方法です。ガス抜きに役立つ、3つのストレッチを解説します。
膝を抱えるポーズ
- あおむけに寝て、片膝を抱えます。
- 息を吐きながら、お腹に膝を引き寄せます。
この動きの際に、お尻を持ち上げた状態で腹式呼吸を数回しましょう。お腹に圧をかけた状態の腹式呼吸により、腸が刺激されガスを排出できます。このポーズは、ベッドや布団上でのストレッチに適しています。
足の上げ下げ
- あおむけに寝て、両膝を伸ばします。
- 足を上げたり下げたりします。
慣れてきたら、座って両手を後ろについた状態でしましょう。便秘解消を促せて、マッサージとともに行うのがおすすめです。
お腹のひねり
- 立って両足を肩幅に開き、右手で左手首をつかみます。
- 息をゆっくり吐きつつ、上半身と腕を右にひねり、10秒間キープします。
- 右側を終えたのち、左側も同様に行いましょう。
仰向けに寝て、両膝を立てた状態で下半身を左右に倒すのもよいでしょう。左右6回ずつを1セット、朝昼晩と行うのがおすすめです。お腹をねじることで圧力がかかり、腸のガスを排出できます。
お腹のガスを抜く方法:3.マッサージをする
お腹のガスを抜くには、腹部へのマッサージもおすすめです。繰り返すと腸内がゴロゴロして、ガスの移動する様子がわかるはずです。
お腹へのマッサージによって腸が内容物を移動させる活動を活性化でき、ガスの排出や便通の改善が期待できます。大腸の経路に沿うように軽くマッサージをしたり、腸の内容物を経路に向かって揉むようにマッサージをしたり、刺激を与えるとよいでしょう。
お腹にガスを溜めないために
お腹にガスを溜めないようにするには、日常生活の習慣が重要です。4つの方法を解説します。
食事は腹八分にする
ガスを溜めないためには、食事を腹八分にすることが大切です。食べ過ぎ・飲み過ぎや不規則な食事はガスが溜まり、お腹が張りやすくなります。規則正しい時間の食事やしっかりと噛むことを意識しましょう。
食物繊維を摂る
食物繊維を多く摂ることで、便秘の予防につながります。食物繊維には「不溶性食物繊維」という腸を動かし便通を促すものと、「水溶性食物繊維」という便をやわらかくし出やすくするものがあります。ただし、食物繊維の過剰な摂取はかえって腸内のガスを増やす可能性があるため、極端に摂取量を増やすのではなく適量にしましょう。
適度に運動する
適度な運動習慣は腸内の善玉菌を増やし、腸の活動を活発にしてくれます。そのため、お腹のガス増加を防止するには適度な運動が適しています。なかでも、ランニング・サイクリングなどの有酸素運動がおすすめです。運動不足は腸の活動低下につながるため、適度な運動を意識しましょう。
ストレスを溜めない
ストレスを溜めないことも、お腹のガスを溜めないことに関係があります。ストレスは胃腸の働きに影響を与え、お腹の張りにつながるためです。日頃からストレスを溜めないよう、適度な運動や十分な休養・睡眠を意識しましょう。
ガスを減らすにはごぼう茶もおすすめ
食物繊維が豊富に含まれているごぼうには、腸内環境改善効果が見込めます。定期的に摂取が難しい場合は、ごぼう茶がおすすめです。ごぼう茶はごぼうから作られたお茶で風味を感じられるため、ごぼうが好きな人にもぴったりです。
まとめ
ごぼうには水溶性の食物繊維と不溶性の食物繊維が含まれており、1日1本程度(約160g)を摂取の目安として一定期間摂取しましょう。一方で、過剰に摂取するとガスの原因になる可能性があります。ガスが溜まる原因には多くの場合、食事や生活習慣が関係しています。腸内環境の改善には、ごぼう茶の摂取もおすすめです。
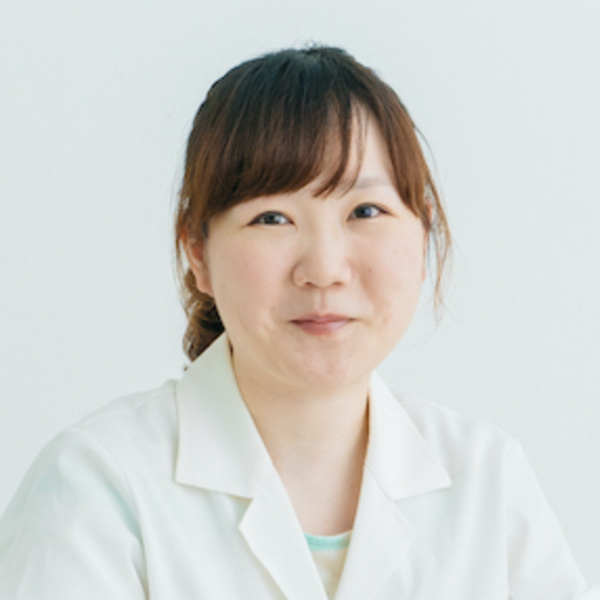
監修岡本妃香里(薬剤師)
2014年に薬剤師の資格を取得し、そこから4年間、大手のドラッグストアで調剤と市販薬の販売に携わる。現在は医療ライターとして、ネットでいちばん身近なドラッグストア「マリモドラッグ」を運営中。「選び方がわからない」「どの市販薬が自分に合うかわからない」というお悩みに対し、市販薬の正しい知識について発信中。
ネットでいちばん身近なドラッグストアに。
マリモドラッグ

